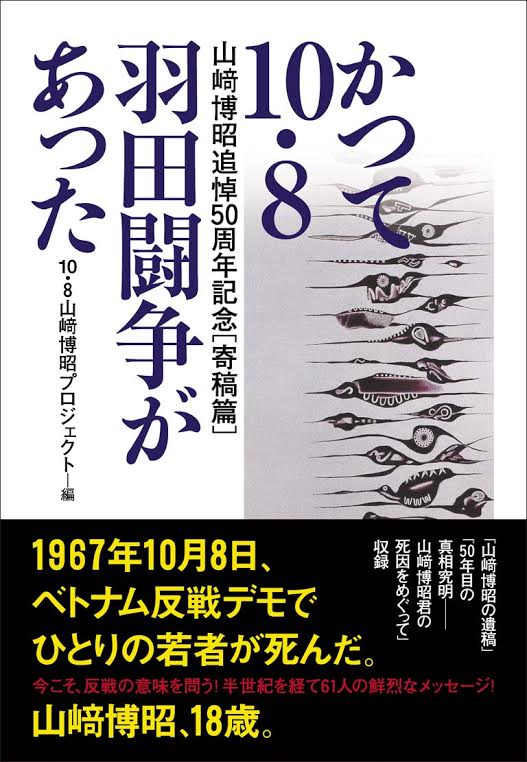反核をめぐって ― 反核兵器と反核発電は単一不可分の課題/山本義隆
反核をめぐって
―― 反核兵器と反核発電は単一不可分の課題である
被団協ノーベル平和賞受賞について思うこと
山本義隆
1.石破首相と潜在的核抑止論
日本原水爆被爆者団体協議会(被団協)が2024年のノーベル平和賞を受賞した。ノーベル平和賞委員会は過去にはいくつか問題のある判断をしてきたが、今回の決定については、日本の被爆者のこれまでの運動を評価したものとして受け止めることができる。12月10日の授賞式での被団協の受賞講演の基調は、核兵器と戦争の廃絶であり、核兵器禁止条約の普遍化にある。もちろん多くの日本人の望んでいることである。
このことに関連して、石破茂首相の発言が翌日の新聞に記されている:
10日の衆議院予算委員会で首相は「長年の核廃絶に向けた発信の努力が報われた。…… 本当に御苦労様でした」と日本被団協の活動をたたえた。
一方で、北朝鮮や中国、ロシアの核保有国に囲まれている状況に触れ、「(核を含む米国の戦力で日本への攻撃を思いとどまらせる)拡大抑止を否定するという考え方を私は持っていない」と強調。(『朝日新聞』2024‐12‐11)
何のことはない。最大の核兵器保有国である米国に核廃絶を訴える積りは毛頭ないどころか、日本は米国の核兵器に依拠すると表明しているのである。これでは被団協のこれまでの活動に対する「本当にご苦労様でした」というねぎらいが、このうえなく空疎で、白々しく聞こえる。
しかし、かつて小泉内閣の防衛庁長官さらに福田内閣の防衛大臣を務めた軍事オタク石破の本音は、そこに止まらない。福島の原発事故の年に石破は「原発を維持するということは、核兵器を作ろうと思えば一定期間の内に作れるという〈核の潜在的抑止力〉になっていると思っています。逆に言えば、原発をなくするということはその潜在的抑止力を放棄することになる」と語っていたのである(『SAPIO』2011-10-8)。そもそもが「核の抑止力」なるものが幻想だということはさておき、米国の「核の傘」に頼るばかりか、その気になれば日本自身がいつでも核武装できる、つまり核兵器(原爆)を作りうる状態 ―― 核兵器製造に必要な施設と技術と人材を保有し、核分裂性物質つまり濃縮ウランないし高純度プルトニウムを相当量備蓄している状態 ―― を維持しておかなければならないというのが、石破がエネルギー政策をこえて日本の核発電に託している目的なのである。「平和利用」と語られている現在日本の核開発 ―― 原子力発電所(原発)の建設・使用 ―― は将来的な「軍事利用」としての核兵器保有への途に通じているのである。その意味において日本の核開発は「潜在的核武装」と言うべきものなのである。
戦後の日本で最初に核開発 ―― 原発の導入 ―― を牽引したのは、核兵器・核技術を持っている国だけが戦後世界で「一流国」たりうると信じて止まない、ナショナリスト中曽根康弘であった。そして、一刻も早くかつての大日本帝国の栄光を取り戻したいと願う中曽根の「核ナショナリズム」に始まった日本の核開発に、単なるエネルギー問題をこえる「潜在的核武装」という明確な政治的意味を与えたのが、岸信介であった。戦前、商工省(戦後の通商産業省=経済産業省の前身)官僚として軍と一体となって高度国防国家建設にむけて戦時統制経済を指導し、また東条内閣の商工大臣とし1941年の日米開戦の詔勅に署名し、敗戦後、戦犯容疑で逮捕されたものの何故か起訴されることなく釈放され、その後、政治家に転身し、1957年に首相の座に登りつめた岸信介であった。
岸は後に『回顧録』で「昭和33年〔1958年〕正月6日、私は茨城県東海村の原子力研究所を視察した。日本の原子力研究はまだ緒についたばかりであったが、私は原子力の将来に非常な関心を寄せていた。 原子力技術は平和利用も兵器としての使用も共に可能である。どちらに用いるかは政策であり国家意志の問題である。日本は国家・国民の意志として原子力を兵器として利用しないことを決めているので、平和利用一本槍であるが、平和利用にせよ、その技術が進歩するにつれて、兵器としての可能性は高まってくる」と回想しているが、それだけではない(岸『岸信介 回顧録』p.395f.)。その後の講演では「平和利用ということと軍事利用ということは紙一重の相違である。ある人は紙一枚すらの相違はないといっている。今日の原子力のいろいろな利用というものは、いうまでもなくみな軍事的な原爆の発達から生まれてきているものである。平和的利用だといっても、一朝事ある時にはこれを軍事的目的に使用できないというものではない」とあけすけに語っていたのである(岸 『最近の国際情勢』p.13)。
これは後の回想で、これだけでも岸が日本の核開発に託した狙いが透けて見えるであろうが、実際には現役の首相時代には、岸はもっとストレートに核武装願望を表明していたのである。当時の日本経済新聞の政治部で岸番の記者であった大日向一郎が、のちに研究者からの聞き取りで証言している。きわめて重要な割にはこれまで何故か注目されることがなかった処なので、少し長いが、該当部分を全文引いておこう。
ナショナリズムといえるかどうかわかりませんけれど、とにかく自分の国は自分で守るんだ、その基本は軍備なんだ、だから核武装は絶対必要なんだってことを、〔岸首相は〕国会で答弁していますよ、だから日本が核武装して、日本のロケット技術が進歩すれば、もし日本に核を打ち込もうというロケット基地があれば、外国だって〔日本は〕そこを攻撃できますよ、これ憲法違反じゃありませんということを、本会議か、外務委員会かで答弁していますよ。 だから後になってからでしたけど、「核武装するとしたら核実験しなくちゃいけない、どっか沖縄あたりの離島で適当なところがないかね」なんてね、僕に聞いたことがありました、だから「南洋、マーシャル群島かなんかで、旧日本帝国時代の国王と話し合って借りたらいかがですか」といったんですが、なんか核武装についてえらい熱心でしたよ。(『岸信介政権と高度成長』東洋経済新報社 2004, p.196f.。強調山本)
本音であろう。それにしても敗戦から未だ十余年、太平洋戦争末期に「本土決戦」の予行演習を押し付け地獄をもたらした沖縄をなんと見ているのか、敗戦の受け入れを拒み続けたために招いた広島と長崎の悲劇をなんと見ているのか、かつて事実上の植民地支配をつづけ、そのうえ戦禍で荒廃させた太平洋の諸国をなんと見ているのか、みずからひき起こした戦争がもたらした惨禍に対する驚くべき無自覚と、民衆の負わされた痛苦に対するあまりの鈍感さに、言葉もない。近頃横行しているフェイクではない。東大名誉教授・中村隆英と東洋英和女学院大学の研究者・宮崎正康の共同編集になるれっきとした研究書に掲載されている、大新聞の記者のインタビューの一部である。
戦後の日本が「平和利用」に限って核開発・原発使用に乗りだしたというのはあくまで表向きの話であり、実際には将来的な「軍事利用」も見すえたうえで、「平和利用=非軍事利用」に取り組んできたのであった。
2.核武装をめぐるその後の動き
その中曽根の核ナショナリズムや岸の核武装願望は、その後も日本の防衛政策の深層底流として、自民党の中核部分や外務省高官や一部の保守的な政治学者の間に連綿と継承され、中国の核実験や核兵器不拡散条約(NPT)等の問題が起る度に表層に露呈してきた。1970年2月、当時の核兵器保有国である米英ソ仏中の五カ国の核兵器の削減をはかり、同時にそれ以外に核兵器保有国が広がらないようにするためのNPTに日本は署名したが、国会での批准は76年6月に大きくずれこんだ。それというのも、自民党内部の相当数の核武装願望勢力が、正式に加盟の手続きになる批准に抵抗したからであった。
NHKスペシャル取材班が出版した『核を求めた日本 ―― 被爆国の知られざる真実』(光文社 2012年)には書かれている。
NPTについては、加盟をめぐって当時の下田武三駐米大使や牛場事務次官が「現時点では核武装しないことは日本国民の総意だが、核武装するかどうかの最終決定は将来の世代が決めるべきだ」とか「NPTに加入する結果、永久に国際的な二流国として核付けされるのは絶対に耐え難い」などと疑問を投げかけたり、自民党の一部議員からも強硬な反対意見も出されたりしていたことが、外務省OBへの取材や入手した外務省の資料などからわかった。(p.30)
これからわかるように、外務省と自民党議員の一部は、NPT加盟に当時抵抗していたのであった。外務省には、戦後20年以上も経って、なお中曽根以来の核ナショナリズムが脈打っていたことが読み取れる。
NPTが議論されていた当時、米英ソ仏中の核兵器保有国以外で、核武装の能力つまり核兵器を自力で作る能力を有していた国は、日本と西ドイツの二国であった。そして日本の外務省は、NPT条約の真の狙いを日本と西ドイツに核武装させないためだと理解していた。実際にも1969年、日本の外務省国際資料部の調査課長・村田良平が、訪日したドイツの外交官エゴン・バールに対して、日本とドイツでNPT条約を遁れる道を協議することを秘密に提案していたのであった。NHKスペシャル取材班の書には、その日本外務省がもちかけた西ドイツ外交官との秘密協議の狙いとその内容について、村田本人による後の証言が載せられている。
「やはりNPTというあの条約の当時の一番重要な狙いが、日本と西ドイツの両国に核武装させないということにあったからですよ。」(p.43)
「何とか核兵器を持てるきっかけを作るよう努力すべきだと思いました。さりとて具体的にNPTの会議でそんなもの提案できませんからね。全部裏取引ですから。意見交換をずっとやって、それで何とかNPTを覆す方法がないだろうかという話をしたのが、〔西ドイツの外交官〕バールが日本に来たときの協議です。」(p.43f.)
それに対する、西ドイツ外交官エゴン・バールの、翌年ドイツで再開したときの返答が、やはり村田の言葉で記されている。
「一番記憶に残っているのは、エゴン・バール自身の言葉です、『こうしてお互いに話してきましたが、日本とドイツが(NPTの義務を免れるという)特別待遇を受けることは不可能だと結論づけないといけません。これからの我々の仕事は、核を持っていてもその意味がないというように国際政治の基本をつくり替えていくほかないのです』という意味の深い言葉を言いました」(p.44f.。 太字強調は山本による)
一体どちらが、世界に対して「唯一の被爆国」だとつねづね称してきた国なのか。核をめぐるこの日本とドイツの差は、核発電に今なお固執している日本と核発電を放棄したドイツの差として、現在、歴然と現われている。そして1969年の外務省外交政策企画委員会の「我が国の外交政策大綱」には「当面核兵器は保有しないという政策をとるが、核兵器製造のポテンシャル(能力)は常に保持するとともにこれに対する掣肘(周囲から干渉)を受けないように配慮する」と明記されていたのである(『毎日新聞』1994-8-1)。
結局、核兵器不拡散条約(NPT)をめぐる、日本の政府中枢におけるこれらのに動きに一貫しているのは、今すぐとは言わないにせよ、将来的な核武装にむけてフリーハンドを残しておかなければならないという、岸信介以来、日本政府中枢に継承されてきた政治的意志なのである。
3.そして現在の問題
この点では、現在日本政府が核兵器禁止条約に加入しようとしないことも、基本的には同じ理由であろう。被団協は石破首相に、核兵器禁止条約締約国会議へ、せめてオブザーバーとしてでも参加してもらいたいと直接訴えていたのであるが、1月25日の『毎日新聞』の記事には、「政府は、3月に米国で開かれる核兵器禁止条約締約国会議へのオブザーバー参加を見送る方向で調整に入った」とあり、「日本被団協『政府に腹立つ』」との見出しがつけられている。被団協の長年にわたる努力がノーベル平和賞の受賞という形で国際的に広く認められた直後の国際会議であり、国を挙げて核兵器禁止を世界に訴えるまたとない機会であるが、日本政府はその絶好の機会をミスミス逃すことになる。
そのことは、日本のマスコミは指摘しないが、外国から見れば、日本政府は将来的な核武装という選択肢をやはり手放そうとはしていないのだ、と判断されることを意味している。
外国からどのように見られるかという点では、つぎの事実を挙げることもできる。ごく最近のことだが、岸田内閣の閣僚であった河野太郎が石破政権誕生直前の自民党総裁選に立候補した際の選挙公約に、原子力潜水艦(原潜)保有を掲げていた。『昭和史の事典』(東京堂出版)には「原潜は原子力エンジンを装備しているだけではなく、核兵器の搭載を前提とした戦艦であり」と明記され、吉岡斉の『新版 原子力の社会史』(朝日新聞出版)にも「1950年代に入ると米ソの核軍拡競争が、核弾頭と運搬手段の両面で激烈に展開された。その成果として水爆が開発され、……大陸間弾道ミサイル、潜水艦発射弾道ミサイル、長距離戦略爆撃機という戦力の三本柱が樹立することになった」と記されている(p.12)。酸素を消費しないので長時間にわたって潜航を続けられる原潜は、居場所を突き止められないミサイル発射基地として、軍事的に大きな価値を有しているのである。ということは、現代の国際政治や核戦略理論の常識からすれば、自衛隊の原子力潜水艦保有を掲げることは、将来的な自衛隊の核武装を表明することと事実上同義なのである。それを政権党の有力政治家が政権党の総裁選の公約に掲げたということは、外国から見れば、当然ながら、日本政府内部における核武装の野心の存在を示すものということになる。
その事実はまた、多くの論者が一貫して認めているように、日本の核開発の直接的目的が、核産業・原発メーカーの育成にあったということからも窺い知れる。実際にも世界トップクラスの原発メーカーを、三菱、日立、東芝と三社も有しているのは日本だけである。そればかりか、福島原発の事故の後、当面原発の新規建設が見込まれない状態で、経済産業省がもっとも力を入れていたのが核技術の維持 ―― 設備の維持と人材の養成、そして集団的な経験の継承 ―― であったのだ。
それでなくとも、世界最悪と見られる福島の原発を経験した日本が、もはや経済的にもペイしなくなっている原子力発電に今なお固執していることは、日本の核開発・核使用の目的が経済だけにあるのではない、その裏には軍事目的があると、近隣のアジア諸国から判断されていると見てよい。そしてそのことは、アジアに余計な緊張をもたらし、核廃絶をより困難にしていることになる。
実際にも福島の事故ののち、原発の安全性や経済性を公言できなくなった核発電推進勢力は、日本の核開発には、エネルギー政策だけではなく、「安全保障」という目的が潜んでいることを隠さなくなった。自民党と公明党は原子力基本法に書かれている「核開発の目的」に「我が国の安全保障に資すること」を加える提案を行ない、当時の政権党であった民主党もそれを受け容れたのである。民主党内の電力総連出身の国会議員は、核発電維持という点では親会社である電力会社と一体である。
そして今回、政権党である自民党の総裁に、さらには日本の首相に選出されたのが、他でもない、福島の原発事故の直後に「潜在的抑止力」のためにあくまで原発使用を継続しなければならないと語った石破本人なのである。その石破がその潜在的な「核抑止力」の目的のために必要なこととして明言したのは、「〔ウランの〕濃縮と再処理に裏打ちされる核燃料サイクルは、回し続けないといけない」ということであった(太田昌克『日本はなぜ核を手放せないのか』岩波書点 p.181)。
これは太田の書からの引用だが、同書には「石破の言う〈技術抑止〉とは、核兵器保有の選択肢を当面は放棄する一方、核分裂性物質〔ウラン235とプルトニウム〕や核兵器運搬手段〔弾道ミサイル〕を開発できる技術力を確立しておき、時の為政者の政治判断で短期間のうちに核保有できる能力を温存することで敵対国の動きを抑止するという安全保障戦略」と解説されている。それは実際には、絵に描いた餅でしかない。そもそも、軍事力の強化、軍事技術の高度化による「安全保障の確保」なるものは、つねに相手国がそれを上回る力をつけることによって無意味化するだけではなく、むしろ危険性がより高まる結果をもたらすことになる。このことは、戦前の列強間の巨大戦艦建造競争や、第二次大戦直後の、米国の原爆独占的所有が直ちにソ連による原爆実験で打ち破られ、それにつぐ米国の水爆開発もほとんど直後にソ連の水爆製造に追いつかれたことで、歴史的に証明されている。インドとパキスタンの原爆開発の競り合いも同様である。それは恐怖の均衡であるが、かつて1937年に一発の銃声から日中戦争が始まったように、偶発的事件が均衡を崩す可能性はゼロではないのである。
4.核燃料サイクルをめぐって
さてここで、石破が語った「核燃料サイクル」という言葉に注目しよう。
原爆には「ウラン爆弾」と「プルトニウム爆弾」がある。天然のウランは、核分裂をしないウラン238が99.3%、核分裂性で原爆の「爆薬」となるウラン235がわずか0.7%、ウラン爆弾は天然ウランから核分裂性ウランの割合を高めて得られる「高濃縮ウラン」を用いるもので、広島に落とされたもの、プルトニウム爆弾は高速増殖炉で得られる核分裂性のプルトニウムを用いるもので、長崎に落とされたものである。つまり核爆弾製造には「濃縮ウラン」ないし「プルトニウム」が必要であり、それらは通常の発電用の原発での使用済み核燃料の再処理と高速増殖炉の運転によって得られるものであり、その過程が「核燃料サイクル」と呼ばれる。
原子炉で発電した後には、当然、使用済みの核燃料が残される。それをそのままゴミとして処分する行き方と、再処理してそこから再使用可能な燃料、つまり濃縮ウランとプルトニウムを取り出す行き方があり、後者が「核燃料サイクル」なのである。前者は比較的簡単で費用もそれほどかからないが、その場合、原発運転後、ただちに使用済み核燃料の最終的処分の問題に直面する。他方、再処理施設、ウラン濃縮工場、そしてプルトニウムを作り出す高速増殖炉よりなる後者の「核燃料サイクル」は、技術的にきわめて困難で、多額の経費を要し、そして同時に核燃料をむき出しにして処理するため危険性も飛躍的に高まる。もちろん危険で厄介な核のゴミも大幅に増加する。しかし日本は最初から核燃料サイクル建設を核開発の第一目標に設定し、戦後最大の国家事業として取り組んできた。
その狙いは、公式には「核燃料の自給」にあるとされているが、それは同時に核爆弾(原爆)に必要な濃縮ウランやプルトニウムを抽出する過程であり、その背後に「核武装能力獲得」の狙いが潜んでいることは、否めない事実である。その意味で核燃料サイクル、とりわけ高速増殖炉によるプルトニウム生産こそ、潜在的核武装の胆であり物質的基盤なのである。実際にも、核兵器不拡散条約をめぐって外務省の内部では、「高速増殖炉などの面ですぐに核武装できるポジションを保ちながら平和利用を進めていくことになるが、これは異議のないところであろう」といったことが議論されていたのである(太田『日本はなぜ核を手放せないのか』p.123)。
現実には、核燃料サイクルは、かつてはウラン資源の枯渇に対するものとして過大な期待が寄せられたことがあったが、現在では、技術的にあまりにも困難で危険性も高く、厖大な費用も必要とし、経済的にはペイしないことがわかっているので、世界的に見れば、軍事目的を離れては事実上見捨てられている。核兵器保有国以外で核燃料サイクルの建設を認められている、正確には米国が認めている国は、日本だけである。そのうえ日本は、外国の施設で作らせた分もふくめてすでに原爆6000個分のプルトニウムを所有しているのである。当然他国は、日本が経済的にはまったくペイしないその事業に固執している裏には軍事目的があるにちがいない、と見ているであろう。
ところで実際には日本の核燃料サイクル建設は、すでに厖大な経費を投入し、年月をかけてきたにもかかわらず、事実上破綻している。再処理施設の建設は年中行事のような完成延期の表明をすでに27回くりかえし、完成のあてはなく、その完成を誰一人信じていない。高速増殖炉の建設も、原型炉「もんじゅ」の破綻で立ち往生している。そもそも核発電それ自体がもはやペイしなくなっているのであり、その危険性はもとより、経済性からいっても、残される核のゴミの問題からしても、核発電自体も核燃料サイクル事業もともにただちに撤退すべきものであることは、あらためて言うまでもない。
しかし日本政府・経済産業省、電力企業、原発メーカーは、それぞれの思惑で破綻した核燃料サイクルに固執し続けている。電力会社は使用済み核燃料の最終的処分という難題を先送りする口実として、原発メーカーは金のなる木として、サイクル建設に群がっているのである。その詳細については立ち入る余裕がないので、小著『核燃料サイクルという迷宮』(みすず書房)を参照して頂きたいが、やはりその根幹にあるのは、日本の核開発をめぐる、単なるエネルギー問題を越える「安全保障」と称される政治的・軍事的野心の存在なのである。そのことこそが、被団協ノーベル賞受賞の1週間後に「原発を最大限活用する」とした安全性も経済性も危惧される新しい(第7次)エネルギー基本計画が政府の意向として示された背景に他ならない。
いずれにせよ、核発電の持続、核燃料サイクルの建設、そして潜在的核武装路線の維持は、現在日本の核武装能力の維持、ひいては将来的な日本の核武装に直結する、どのひとつも欠かすことのできない一環として、権力サイド ―― 経済産業省、外務省、自民党の中枢、財閥系原発メーカーと関連企業、電力会社、そして電力会社やメーカーと一体となっている御用学者集団 ―― では位置づけられ、固執されているのであり、それらを一体として拒否しないかぎり「真の反核」はあり得ないことを、「反核」運動は認識し決意しなければならないであろう。
被団協ノーベル平和賞受賞について思う処である。 2024年2月
ふくしま共同診療所 医師連絡会の依頼で、同会発行の『被曝・診療 月報』第66号(2025年2月1日)に同じ標題の論考を寄稿したのですが、字数制限を若干超えていたので、少し削りました。これは、その、元の原稿に更に筆を加え、書き直したものです。 山本義隆